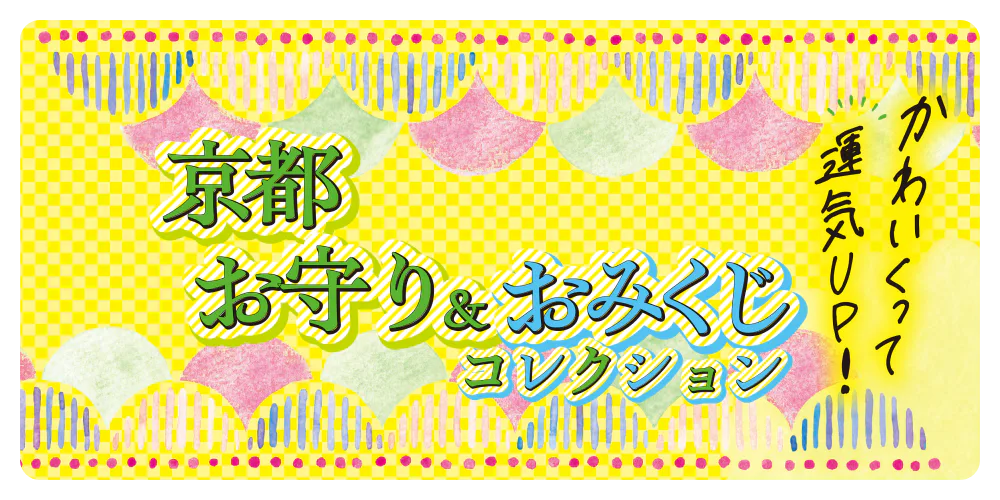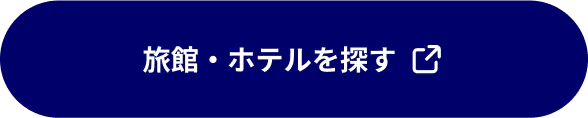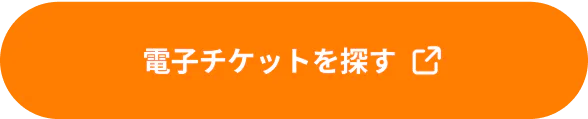神社やお寺を訪れたら、やっぱり気になるお守り&おみくじ。ついつい気になるかわいいアイテムでご利益を持ち帰ろう!

健康
四季守
1500円
季節によりデザインが変わるレース生地のお守り。写真は5月の葵
下鴨神社(賀茂御祖神社)
しもがもじんじゃ(かもみおやじんじゃ)
参道を覆う糺の森は、縄文時代の植生を残す原生林で、マイナスイオンあふれるパワースポット。境内には葵祭で斎王代が身を清める御手洗池も。五穀豊穣や心願成就、安産などさまざまなご利益があるとされる。
市バス停下鴨神社前からすぐ
左京区下鴨泉川町59
参拝無料(大炊殿、御車舎、河合神社の特別拝観は共通1000円)
本殿6~17時(特別拝観は10~16時)
無休
200台

良縁
ハートアジサイのお守り
各1000円
愛が込められたハート形のお守り。ころんとした形がキュート
三室戸寺
みむろとじ
宝亀元年(770)、光仁天皇の勅願で創建された花の寺。
京阪三室戸駅から徒歩15分
宇治市莵道滋賀谷21
1000円
8時30分~15時40分最終受付(11~3月は15時10分最終受付)
8月中旬、12月29~31日
300台

美容
櫛のおまもり
800円
つげ櫛をモチーフにした小さなお守り。ひとつひとつ柄が異なるので選ぶのも楽しい
御髪神社
みかみじんじゃ
百人一首にも詠まれた小倉山の麓に鎮座する、髪にまつわる神社。国家試験の合格祈願に訪れる専門学生をはじめ、芸能人も訪れるという。境内には髪を納祭する髪塚がある。

身体健全
身まもり
各1000円
ご神紋の二葉葵をモチーフにした、パステルカラーがかわいいお守り
上賀茂神社(賀茂別雷神社)
かみがもじんじゃ(かもわけいかづちじんじゃ)
京都最古の神社で、御祭神の賀茂別雷大神は、大自然の力を支配し、あらゆる災厄を祓う神様として信仰されている。境内には『小倉百人一首』にも登場する、ならの小川が流れる。
市バス停上賀茂神社前からすぐ
北区上賀茂本山339
参拝無料(本殿、権殿の特別参拝500円)
5時30分~17時(楼門内は8時~16時45分)
無休
170台(有料)

祈願成就
玉の輿お守
800円
八百屋の娘であったお玉の方にちなんだ、京野菜の柄がかわいらしいお守り
今宮神社
いまみやじんじゃ
徳川綱吉の生母・お玉の方桂昌院ゆかりの神社で、本殿には健康長寿と良縁開運の神を祀る。持ち上げて軽く感じれば願いが叶うという神占石・阿呆賢さんにも願いをかけてみて。

縁結び
むすび守文型
各1000円
男女間の縁結びをはじめ、人と人、子授けなど、さまざまな縁を結んでくれる
貴船神社
きふねじんじゃ
京の水源を守る神様で、中宮は縁結びの神様・磐長姫命を祀ることから「結社」と呼ばれる。本宮へと続く長い階段の両脇には灯籠が並び、夏は爽やかな青もみじ、秋は鮮やかな紅葉との競演を楽しめる。

スポーツ上達
闘魂守り
700円
試合で勝利に導いてくれたり、普段の練習でけががないように守ってくれる
白峯神宮
しらみねじんぐう
スポーツ上達の神を祀る。蹴鞠の宗家・飛鳥井家邸宅跡にあり、サッカーならびに球技スポーツ関係者の参拝が多い。

幸福鳩みくじ
500円
かわいい素焼きの鳩が幸運のメッセージを届けてくれる。おみくじは境内の柳の枝に結ぼう
六角堂 頂法寺
ろっかくどう ちょうほうじ
聖徳太子が創建したと伝わる。本堂の形が六角形であるため「六角堂」と呼ばれている。

うさぎみくじおまもり
各500円
ウサギは子授けや安産の象徴とされる。長い耳から、幸せな知らせが入るともいわれる
東天王 岡﨑神社
ひがしてんのう おかざきじんじゃ
子宝に恵まれた御祭神にあやかり、子授け安産の神様として親しまれている。境内には子授けうさぎが鎮座している。

りすのおつげ
800円
花見の名所であることにちなみ、リスが桜の花を抱えたデザイン。大きなしっぽがかわいい
平野神社
ひらのじんじゃ
平安遷都の際に奈良から遷されたことが始まり。江戸時代以降、桜の名所として名が広まり、境内の約60種の400本にもおよぶ桜は桜保存会によって守り続けられている。

牛みくじ
各500円
菅原道真と縁の深い牛にちなんだおみくじ。イエローやピンクなど全5色を用意
菅原院天満宮神社
すがわらいんてんまんぐうじんじゃ
菅原道真の邸宅・菅原院が広がっていたという土地に立つ。境内には道真の産湯に使われたという「初湯の井戸」も。

かえるみくじ
500円
「福を迎える」「若返る」など、語呂合わせで縁起がいいとされる勝林寺のアイドル
勝林寺
しょうりんじ
東福寺の塔頭寺院。坐禅や写経体験などを行っているほか、華やかな花手水も話題。

虎みくじ
700円
モチーフは毘沙門天のお使いとされている虎。丸いフォルムと表情にときめく
両足院
栄西が開いた禅寺・建仁寺の塔頭。通常非公開だが、半夏生が咲く初夏には特別公開を行う。